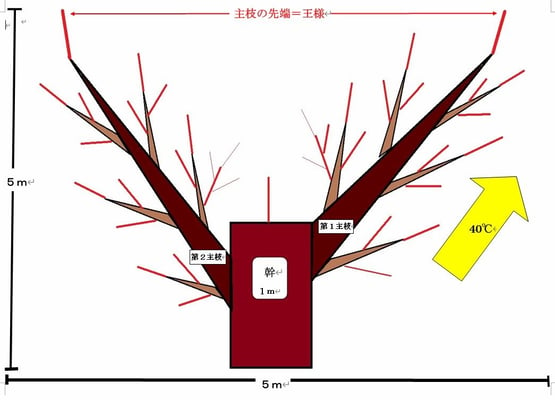【栗の裏情報⑪ 樹形の話】
能登栗農家の松尾です🌰
昨年は調子にのって、
全10話の【栗の雑談】を投稿しました😅
「知るって美味しい」と言いますが、
何も知らずに食べるより、
何か情報や価値を頭に入れて食べるとより美味しく感じる。
そう思って、今年もゆる〜く生産者の裏側を情報発信させて頂けたらと思っています。
興味ない方はスルーしてください😊
今年初の話題は樹形編です。
美味しい果実のできる樹形があるってご存知ですか?
本当に樹形によって味は変わるのですよ😲
松尾栗園の理想の樹形は、
直径5m
樹高(主枝の先端) 5m
主枝の角度 40℃以上
主枝の本数 2本か3本
樹の中心部(幹)地上1m地点から
40℃の角度で高さ5mに到達する場所まで枝を育てていくと、
長さ3.3mの主枝ができます。
この主枝を基軸にして、側枝や結果母枝を毎年育成します。
この40℃以上の主枝の角度にとても大事な意味があるのです。
枝はみんな一番高い所に行きたくて仕方がありません。
なぜなら、一番陽当たりが良くて、
一番光合成ができる☀
さらに、地下部(根)からは最優先で栄養分が送られてくる😋
樹の頂上。
そこはもう枝にとっての楽園なのです✨
栗の樹は頂芽優勢という性質を持っています。
頂芽には根から転流される「サイトカイニン」という植物ホルモンが蓄積します。
サイトカイニンは生長を促進するホルモンです👆
頂芽は下部の芽と比較してサイトカイニン活性が高いため、
優先的に光合成産物や栄養分が供給されます。
逆に「オーキシン」という植物ホルモンは、
頂芽で生産されて地下部の根へ転流します。
このオーキシンは下部の芽の成長を抑える働きをします👇
つまり、
その主枝の中で頂上部を奪取できた枝は、
自分自身はサイトカイニンの支援を受けてぐんぐん成長し、
下部の枝たちはオーキシンが抑え込んでくれるから、
もう天下は安泰です🗽
ずっと楽園で優雅に過ごすことができます✨
だから、
一番高い所へ行けるチャンスがあるならば、
枝たちは我先にと頂上部(楽園)を奪い合うわけです。
頂上部の奪い合いが起こると、
それぞれの枝を伸ばすことに栄養分をどんどん使ってしまう。
花や果実に回す分は後回し…😭
花も咲かない、実をつけない、
とにかく枝ばかり伸ばすことに必死…😱
何のために栗農家やっているんだろう???
美味しい栗を作るためなのに〜!!!
というわけで、
枝たちに頂上部の奪い合いを起こさせないことが何より大事。
頂上部の奪い合いは主枝の角度不足で起きやすくなります。
角度が低いとオーキシンが主枝の下部を流れてしまい、
抑制力が働きません。
どの枝にも頂上部を狙えるチャンスが生まれてしまいます。
はっきり優劣がつかないと、
いつまでも争いは続きます💣
で、結論。
主枝に40℃以上の角度を付ける!
さらに、
主枝の先端に絶対的な王様となる枝を1本君臨させればいいのです👑
角度40℃、高さ5m先の頂上部に誰が見ても明らかな王様がそびえ立っている。
あの高さには今から頑張っても届かない。
あの王様にはサイトカイニンが付いているし…。
俺たちはオーキシンが圧力をかけてくるし…。
すると、無駄な争いが抑えられ、
頂上部の王様から順に栄養分が均等に分配されていくのです。
王様は決して養分を独占しません😍
各枝の徒長が抑えられるので、
果実への養分分配率がぐっと高まります🌰
果実の味は光合成産物によって作られていきます☀
当然、光合成生産量には限界があリます。
無駄なく果実に分配するために、
樹形の仕立て方が大きな鍵となってくるのです。
あまり主枝の角度が急過ぎるのはNGです。
高く育ち過ぎて樹の内部に日陰を作ってしまうのと、
いずれ邪魔になって強剪定することにつながります。
強剪定をすると、オーキシンの抑制力が低下。
さらに、根から吸い上げた水と養分が残った芽に集中して、
もう樹のあちこちから徒長枝多発…
枝たちの大戦争が始まります🆚
あっ、もちろん果実の成らせ過ぎもNGです。
あくまでも光合成生産量で分配できる範囲に抑えないと、
小粒で糖度が低い果実ばかりななってしまいます。
この角度40℃、長さ3.3mの主枝を1本の樹に等間隔で2、3本配置します。
各主枝ごとに王様を作るので、
1本の樹に2、3人の王様が誕生します👑👑👑
剪定=樹形作り=果実への養分分配の道筋作り
光合成産物をどれだけ果実に分配できるか。
光合成生産量と果実の着果量のバランスが適正か。
味の決め手は樹形といっても過言ではありません。
偉そうな事書きましたが、
今、松尾栗園にある1,100本の栗の樹。
上記のような理想通りの樹…
ごく少数しかありません💦
だいぶ樹形を誤解したまま育ててきてしまったので😭
これから年月をかけて軌道修正していきます😅
最後まで読んで頂いてありがとうございました🙇